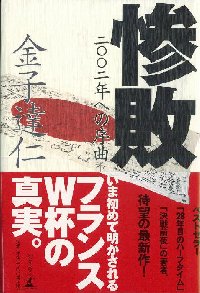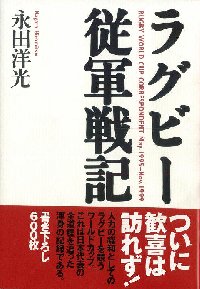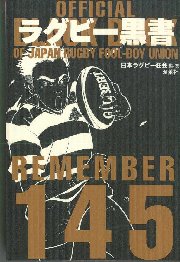本のご紹介
書評というほど本格的なものではありませんが、私が読んだ本の中から、紹介するに値すると思ったものを随時挙げていきたいと思っています。
必ずしも新刊とは限りませんのでよろしく。
→ 『蒼い時』 山口百恵
→ 女刑事・音道貴子シリーズ 乃南アサ
→『ベルリン飛行指令』佐々木譲
→『みにくいあひる』 『なんて遠い海』谷村志穂
→『星を継ぐもの』『ガニメデの優しい巨人』『巨人たちの星』J=P=ホーガン
→『高野山龍泉院過去帳の研究』倉木常夫
→『遺された親たち』佐藤光房
→『惨敗』金子達仁
→『ラグビー従軍戦記』永田洋光
→『午前三時のルースター』垣根涼介
(改訂:2021年4月28日 初出:2021年2月20日)
-
ようやく山口百恵と向き合う
『蒼い時』 1980年 集英社 / 1981年 集英社文庫
著:山口百恵
原著は1980年、文庫版の初版は1981年ですが、今回読んだのは2019年7月の第65刷(!)です。
おおよそ同年代(いま50代)の私はリアルタイムで山口百恵を知る世代です。この本の存在ももちろん出版当時から知ってはいました。
しかし何となく斜に構えていた当時十代の私にとって、同世代の超有名芸能人が書いた“タレント本”(と、いう呼称が当時あったかどうか定かではないのですが)、は素直に手に取れる本ではなく、アラ還に近づいた今日まで未読のままで来てしまいました。
(ついでに記憶をたどると、この出版のさらに少し前、山口百恵のコンサートを私は生で見ています。おそらく1975年か76年ごろ、つまりTVドラマ『赤いシリーズ』等で人気が沸騰したころ、記憶が正しければいわき市の常磐市民会館でした。…いま思えば、あんな片田舎の小さな会場でどうしてそんな企画が実現したのか不思議ですが、とにかく会場が満員だったことしか憶えていません)
今となっては言うまでもないことですが、山口百恵が他の歌手や芸能人たちとは別格の存在であることは、当時すでに多くの識者が気づいていました。菩薩である、と喝破した平岡正明しかり、篠山紀信しかりです。しかし私がその“凄さ”に気がついたのはもっとずっと後、20代をすぎてからでした。
先日(2021年1月30日)、NHK総合でその山口百恵さんのラストコンサートが放送されました。“一回限りの再放送”という謳い文句もあってか、ずいぶんと反響もあったようです。これを機会にと思い、未読だったこの本を今回はじめてきちんと読みました。
読んでみて、いまさらながらその中身の濃さに驚きました。
「…活字で自分を表現していくということは、正直なところ、苦痛を伴う作業だった。
無意識のうちに忘れようとしていた場面をあえて思い起こすところから始まり、事実は事実として嘘のないように書いていく。
これは、自分が最も知りたくなかった自分の醜さをも、自らの手で暴くことだった。」
―──『蒼い時』山口百恵 集英社文庫 208ページ
執筆時、たかだか20歳前後だった彼女の、この文章の鮮烈さ、鋭利さ、真摯さ。
紡ぎ出される自らの内面、特に出自と恋についての率直さ、純粋さ。
一説では、この本はタレント本によくあるゴーストライターがおらず、すべて彼女自身が書き下ろしたものだと言われています。読んでみればそれも納得で、これは確かに正真正銘の本人でなければ書けないであろう生の声だと感じさせます。
引退で失われたものは、不世出の歌手だけではありませんでした。
この文才を見いだした残間里江子恐るべし。
そして恐るべし山口百恵。
もし未読の方がいれば、とにかく読んでおくことをお薦めしたい一冊です。
(2016年9月10日 記)
-
いま、音道貴子に会いたい
長編『凍える牙』 1996年4月 新潮社 / 2000年2月 新潮文庫
短編『花散る頃の殺人』 1999年1月 新潮社 / 2001年8月 新潮文庫
長編『鎖(上・下)』 2000年10月 新潮社 / 2003年12月 新潮文庫
短編『未練』 2001年8月 新潮社 / 2005年2月 新潮文庫
短編『嗤う闇』 2004年3月 新潮社 / 2006年11月 新潮文庫
長編『風の墓碑銘(エピタフ)(上・下)』2006年8月 新潮社 / 2009年1月 新潮文庫
著:乃南アサ
ときたま、無性に小説が読みたくなるタイミングが来る。この夏のターゲットは乃南アサの「音道貴子シリーズ」。
この物語は第一作の『凍える牙』を発行後ずいぶんたってから読んだのだが、続編に当たるシリーズの存在を知りながら、その後はこの2016年まで未読のままにしていた。おもしろくなかったのかというとこれが逆で、非常におもしろかったがゆえにあまり一気に読み進んでしまうのがもったいなく、一日延ばしにしたまま数年が過ぎてしまった。しかしこの夏、ふいに我慢が限界に達し、買ってあった続編すべてを、それこそ一気に読破してしまった。
音道シリーズの魅力は、警察と犯罪の物語を女性の視点で描いている点なのだが、特筆すべきは主人公の音道貴子が決して“スゴ腕女刑事”ではない点にある。女刑事というと例えば大沢在昌の河野明日香(『天使の牙』)や誉田哲也の姫川玲子(『ストロベリーナイト』)、TVドラマ先行では「アンフェア」の雪平夏見、あるいは「BOSS」の大澤絵里子などが浮かぶ。彼女たちは概して上昇志向があり、能力的にも例えば男勝りの格闘力や射撃力、または特殊能力を持ってたりして、物語が始まった時点で既に周囲から一定の評価を得ていたり、一部は既に役職者だったりする。
音道は彼女たちとは異なり、ごく普通の警察官だ。短大を出て白バイ警官になったのがキャリアの振り出しであり、第一作『凍える牙』では新米刑事で、今のところの最終巻『風の墓碑銘』でもようやく巡査部長になっているに過ぎない。戦闘力に至っては、バイクチェイスが特徴的な『凍える牙』こそ派手な立ち回りも見せるが、以降は自身でアクションシーンに関わることはほとんどなく、銃に至ってはおそらく、長編3作・短編16作のシリーズ全編にわたってただの一度も発砲していない。
そのいわば“平凡な女刑事”であることが、おそらくはこのシリーズ最大の魅力だ。言い換えれば、この国の警察社会ではまだまだ十二分に、女刑事であるだけでドラマの素材になり得るということだ。
その葛藤、つまり貴子を悩ませる種の一つ一つが、つまりはこのシリーズの要諦なので、未読の方々のためにそれに触れることは避ける。しかしこちらは読み進めるうちに当然、貴子に思い入れてしまうわけだから、そうした障害にぶつかるたびに、またか!と舌打ちをすることになる。その意味ではフラストレーションがたまる。ただしこの物語の救いは、女刑事に対置される男の(特に中年男の)デカたち、がそれなりに魅力的に描かれていることだ。副主人公である滝沢保と、短編に2回登場する島本を筆頭に、相棒となる立川署の八十田や隅田東署の玉城、そしてそれらの周囲には、貴子の視点から見ても憎めない男たちが存在している。そうした憎めない男たちと、憎むべき(または哀れむべき)犯罪者との間で、貴子はあくまで地味に、地道に、刑事であろうとし続ける。

…2016年現在、僕が通勤している墨田区の両国界隈は、音道巡査部長が勤務した隅田東署の管轄に重なっている。安田庭園から隅田川沿いに南北に延びる、決して広くない生活道路は、短編で彼女がヤマハのバイクを駆って追跡をしたまさにその道路のはずだ。
今のところシリーズ最終作となっている『風の墓碑銘(上・下)』の刊行は2007年。既に9年が経過している。シリーズもので10年近い空白は大きく、再開が難しいのは承知の上だが、それでもやはり僕はその後の音道貴子に会いたいと思う。40代になった音道はどんな刑事になっているだろう。まだオートバイに乗っているだろうか。警察の現場は、そして恋人との関係はその後の10年でどう変化しただろうか。あるいは刑事を辞めているかも知れないが、おそらくそれならそれで彼女の人生の物語が続いているはずだ。それをぜひ読んでみたい。
乃南先生、続編再開をお願いします!
(2010年1月16日 記)
-
苦難を超え、零戦は欧州の空に舞えるのか?
『ベルリン飛行指令』 1988年 新潮ミステリー倶楽部
1993年 新潮文庫
著:佐々木譲
実はろくに読んではいないのだけど、好きな作家の一人である佐々木譲。
まだ取っていなかったのか、という感じすらある今回の第142回直木賞受賞。(おめでとうございます)
この人は言わずと知れた警察小説の巧者で、例えば2009年に放送されたTVドラマ『警官の血』(テレビ朝日)の原作も有名だ。このドラマはこの年に放送されたドラマの中でも屈指の出来だったが、それが原作の力に依るところが大きかったのは言うまでもない。
さて、受賞記念のご紹介は(受賞作『廃墟に乞う』は未読なので(^^;)、飛行機ネタで恐縮ながら、旧作『ベルリン飛行指令』。


物語の中盤、ベルリンへの出発を控えた主人公・安藤が、某海軍高官(有名な実在の軍人の設定だが、展開の興をそぐので名は伏せる)に述べる次の言葉がある。
「…米国では飛行士を志願する青年は、志願したときすでに百パーセント自動車の運転ができます。内燃機関についての知識を持っています。自分の自動車を持っている青年だって少なくありません。…しかしわたしが霞ヶ浦に入学したとき、自動車の運転ができた者、運転した経験があった者は、わたしを含めてふたりだけでした。事態は今もそう変わってはいないでしょう。我が国で飛行士を養成するとなれば、まず発動機の原理と、発動機つきの乗り物のなんたるかを教えることからはじめなければならないのです」。
かつて日本が戦ったあの戦争の実相と内情を、端的に切り取った名言だと思う。20年前の初読当時から2010年の今日に至るまでずっと、胸の中に残っている。こういう研ぎ澄まされたセリフを読めるとそれだけで嬉しくなる。
緻密に積み積み上げられたディティールの数々が、荒唐無稽な話に十二分の説得力を与えている。この小説を語るときによく言われることだが、実際に零戦が飛行を始めるのは物語も後半をすぎ、最後の三分の一ほどにすぎない。そこまでの三分の二は、いったいなぜ零戦がベルリンまで飛ぶことになるのか、登場人物たちがどんな思惑でそれを考え、関わり、行動したかを描くことに費やされている。その構造体の完成度にこそこの作品の重みがあるのであり、その意味でいわゆる架空戦記物とは完全に一線を画す(当たり前だが)ことは肝に銘じておきたい。
特にパイロット安藤と妹・真理子、そしてその恋人となる山脇(海軍省の役人)の三人の人物造形が見事で、彼らがこの後、本作と共に“第二次大戦三部作”と呼ばれる続編『エトロフ発緊急電』『ストックホルムからの密使』でも活躍するのが納得できる。
声なき主役である飛行機たちにも、作者の緻密な配慮が注がれているのが心地よい。零戦はもちろんだが、その零戦と敵役のホーカー・ハリケーン、そして華麗な模擬空戦を繰り広げるメッサーシュミット。まあこのへんまでは空戦物語の定番だが、インドの藩王のお抱え英人飛行士が乗るカーチス・ジェニーとなると、ある程度の飛行機好きでないと知らないだろう。さらに唸らされたのが回想シーンに登場するドイツの複葉戦闘機ハインケルHe-51。第二次世界大戦前夜、ドイツ空軍勃興期の主力を担った機体だが、玄人好みのこの機種が日本の小説に登場したのは、おそらくこれが最初で唯一ではないだろうか?
登場する機体を列挙すると、零式艦上戦闘機11型、ハインケルHe-51、フォッケウルフFW-190、九六式艦上戦闘機、九六式陸上攻撃機、メッサーシュミットMe-109C、カーチス・ホークIII、カーチス・ジェニー。
また例えば、劣悪な性能だった当時の無線機を改良するために現われるのが、海軍技術将校のM氏…もちろん後の超有名な電機メーカーの創設者…だったりという、興味のある人にはたまらない味つけが随所になされている(ちなみに、M氏が戦時中、海軍の技師だったのは事実)。
続編の『エトロフ発緊急電』『ストックホルムからの密使』がいずれも何らかの授賞をしている(※)のに比べ、無冠の本作は佐々木譲作品の中でもどちらかというと顧みられることが少ない。言わば埋もれた存在だが、読み応えは十分で一読の価値がある。日本では飛行機を主役に据えた冒険小説がそもそも少ないが、本作はそのジャンルの金字塔と言って過言でない。
※ 『エトロフ発緊急電』 日本推理作家協会賞(長篇)・日本冒険小説協会大賞・山本周五郎賞
『ストックホルムからの密使』 日本冒険小説協会大賞
2010/03/06補足
その後よく調べてみたら、本書『ベルリン飛行指令』は発表当時の1988年に第100回直木賞候補に挙がっていました。
内容のおもしろさからして当然と言えば当然ですが、実は今まで知らなかったのでした。(^^;
(2008年4月 記)
-
ハッピーエンドでなくとも、人生は続けなければならない。
『みにくいあひる』 2008年 文藝春秋
『なんて遠い海』 1998年 新潮社(現在は集英社文庫あり)
著:谷村志穂

みにくいあひる
谷村志穂さんの作品と出会ったのは、ラジオドラマが最初だった。インターネットの情報によれば、2000年2月27日のことだ。NHK第1放送、日曜夜の「ラジオ文芸館」で放送された「最終公演、ワーグナー」。遠出の帰り、夜の国道6号を一人で運転しながらカーラジオで聞いたのだが、これにやられた。申し訳ないが、当時、最初から活字を読んでいたらこれほどこの作品と作家に強い印象を持ったかどうか、自信がない。
NHKのサイトを見たが、残念ながらアナウンサーが誰かは分からない。女声だったことは間違いないし、落ち着いた比較的低い声色が印象に残っていることからすると、この番組を担当することが多かった迎康子さんか青木裕子さん、あるいは御大・広瀬修子さん?あたりではなかったかと思う。
とにかく、何の気なしに聞き始めて45分間、終わる頃にはもう引き込まれていてもたってもいられなくなり、翌日すぐに収録された本を注文した。それが『なんて遠い海』。
世間一般では、流行語にもなったルポ『結婚しないかも知れない症候群』、あるいは伊東美咲のラブシーンで話題になった映画『海猫』の原作者として知られるだろうが、この作者の本領はむしろこうした切れ味の良い短編にこそある。その中でもこの「最終公演、ワーグナー」は出色。
短編ゆえあまり紹介しては味わいを損なうが、活字を読んでみて改めて印象に残るのは、主人公みゆきが指揮者・東山に問いかける次の一節だ。
「・・ワーグナーをめぐる問題は、なぜ拒否しないのか?ということです」。
この作品においてワーグナーは小道具に過ぎない。しかし、その小道具の選び方、扱い方、に作家性は間違いなく現われる。リヒャルト=ワーグナーは言うまでもなく社会的・歴史的に微妙な存在だが、この一文を読むだけで、作家がそれについて十分な考察と識見を備えた上でこの小道具を選んでいることが分かる。
そうした真摯さは、この作家の作品全てに通底するように思える。最新作『みにくいあひる』に至るまで、主人公の女性たちは皆、様々な問題や悩みや焦燥を抱え、もがきながら生きている。僕と世代の近いこの作家(1962年生)にとり、その女性たちはすべて、おそらく何らかの意味で自らの分身のはずだ。作家はしかし、そうしたもがきに安易に共感するのでなく、一定の距離を置いて寄り添っている。ただし、それは冷たいというのとは違う。
そんな想いで再読した『なんて遠い海』だが、実は初見の時と少々勝手が違った。8年前は「最終公演、ワーグナー」だけが突出した印象だったのだが、今回はそれ以外の作が意外なほど響いてきたのだ。特に「今日も猫に話しかけてみる」には参った。わずか12ページほどの小品だが、間違いなく手応えがある。当時の僕には感じ取れなかったものが、今になって届いたのだと思う。作家の手腕の確かさを今さらながら感じた瞬間だった。
『みにくいあひる』では、もがきはより深刻に、または多彩に展開している。それはこの間、結婚し子を持った作家自身の経験と無縁ではないだろう。相変わらず、予定調和的な結末とは無縁である。しかしたとえ待ち構えるのがハッピーエンドでなくとも、人生は続けなければならない。彼女たちも、そして周囲の男たちも。
数年後、僕は『みにくいあひる』を再読するのかも知れない。きっとそのときには、また違うものが見えてくるのだろう。そう思える作家と作品に出会えたことは幸運だと思っている。
<補足>
谷村さんのパーソナル・ホームページ(現在はSHIHO'S HOUSE http://www.shiho-net.org)には、かつて書き込み自由のBBS(掲示板)があった。この掲示板は現在のサイトにはもう無いが、その板が生きていたころ、谷村さんは一つ一つの書き込みに自ら丁寧に応答していた。実は私も当時一度、「最終公演、ワーグナー」の感想を書き込んだことがあるが、数日後それにもレスが付いていた。そこには作品と同じ真摯さがあった。
(2008/4月 記)
-
人類とは何か。何処から来て何処へ行くのか。
『星を継ぐもの』 1980年 創元推理文庫(東京創元社)
『ガニメデの優しき巨人』1981年 〃
『巨人たちの星』 1983年 〃
著:J=P=ホーガン 訳:池 央耿
歳をとる、と言うことはJ=P=ホーガンを読んで泣ける、と言うことなのだと44歳の今にして思った。
最近いろいろあって、ここしばらくは昔の本を読み返す時間が増えている。そのなかで改めて思いを強くしたのがJ=P=ホーガンのいわゆる“ガニメアン三部作”だ。

星を継ぐもの (創元SF文庫)

ガニメデの優しい巨人 (創元SF文庫)

巨人たちの星 (創元SF文庫 (663-3))
SF愛好家諸兄には言わずもがなだが、この三部作はSF史のなかで特筆すべき作品。特に第一作『星を継ぐもの』の発表当時はSF界にかなりのインパクトを与えたらしい。私が読んだのは浪人をしていた1982年ごろと記憶するが、改めていま読み返してみても、当時の衝撃と知的興奮は決して色あせることなく再体験できた。私のSF体験などその道のマニアから見たらたいしたものではないが、乏しいその体験から言わせてもらえば少なくとも小説分野ではベストと言って良い。
近未来のある日、月の裏側の洞窟で宇宙飛行士の遺体が発見される。しかし月面基地には該当する遭難者はいない。一体この宇宙服を着た身元不明者は何者?というのが物語の発端。いわば一種の“密室事件”であり、これだけでも十分にSF心をくすぐられる。そして、その遺体が放射性同位体測定でなんと5万年前に死んだものであること、しかも遺体の生物学的特徴がまさに現生人類そのものであること、という謎が次々に投げかけられる。
人物描写がどうかとか、細部の科学的つじつまが合わないとか、些末な難点はいくらでも挙げられるだろう。しかし、最終的に提示されるプロットの壮大さと説得力において、活字を追いながらこれほど興奮させられた経験は少ないし、心地よい呆然に満たされた読後感は今でも新鮮だ。
それにも増して今回、より心を揺さぶられたのは『ガニメデの優しい巨人』だった。
この第二作は、ストーリーのほとんどが研究室で繰り広げられる議論の応酬、という第一作とは少し毛色が変わる。ジャンルとしてはいわゆる“ファーストコンタクト”ものということになるが、描かれたそれはおそらくSF史上まれに見る、幸福でハートウォーミングなものだ。
なかでも、地球に降り立ったガニメアンが、湖畔で観衆の一人の少年とはじめて握手を交わす場面。読んだ当時にも十分に感動的ではあったのだが、いま読み返したらここで思わず落涙してしまった。初見から過ぎ去ったこの20余年の時間が、読む側にも相応の経年変化をもたらしたという例なのだろう。それが進化であるかどうかは置くとして。
さすがに3作目の『巨人たちの星』になるとジェブレン人の造形が類型的に過ぎるし、随所に顔を出す科学万能主義・西欧中心史観がいささか鼻につく。まぁしかし前2作までの登場人物のその後と細部の謎の顛末が語られるので、読み始めたら結局これも外せない。
この作品に出会えたことは幸せだった。そしてまだ読んでいない人はもっと幸せだ。だって、この興奮をこれから初めて味わうことができるのだから。
<ちなみに>
この3作が創元推理文庫に納められていたのは1980年代当時で、2008年現在はこれらは他のホーガン作品とともに「創元SF文庫」になっている。実は蔵書のうち『ガニメデの優しき巨人』がどうしても本棚に見つからず、改めて買い求めたのだが、2007年時点で実に42版(1981年初版)を数えている。作品としていかに息が長く売れ続けているかが分かる。
なお、共通する登場人物が再登場する第4作『内なる宇宙』も1997年に邦訳が文庫化されているが、ストーリィ概略を読んだ限りでは食指が動かず、未読。ただし、wikipediaによれば、未邦訳の『Mission to Minerva』『The Two Moons 』が控えており、題名からして直接的な続編と思われるので期待している。
<補足>
実際の考古学会に似たような衝撃を与えた名高い事例として、アルプス山麓で約5000年前の凍結ミイラ(アイスマン、愛称エッツィ)が発見されたのは、『星を継ぐもの』の約10年後の1991年のことだった。
<蛇足>
映画版『機動戦士Zガンダム』の副題「星を継ぐ者」はおそらくこのホーガン作品からとられているが、作品としての到達点・完成度とも本家に比べると名前負けの感が否めない。
(2000/9月 記)
-
五輪サッカーの日本代表チームは決勝トーナメントの初戦で敗退した。この敗戦はあの“ドーハの悲劇”になぞらえてひっとしたら“アデレードの悲劇”などと言い習わされるのかも知れないが、言わせてもらえば、わたしゃアメリカを侮るとやられると思っていたので意外ではない。
言うまでもないことだが、アメリカという国は特にフィールドゲームの分野では底知れない潜在力を秘めており、慣れない新規分野でも短時間で消化してしまう。ラグビーが好例だったが、サッカーもこれでそのサンプルになってしまった。ろくに試合も見ずに夕刊フジのヨイショ記事ばかり読んでいたらわからないだろうが、事実はなによりも雄弁だ。この両競技で、ナショナルチームの対戦成績の合計は日本の負け越しなのである。
それはともかく、今回の敗退は良くも悪くも現在の日本サッカーの世界レベルを正確に反映していると言っていいのではないか。つまりベスト32よりは確実に上だが、ベスト16は確実とは言えず、ベスト8から上に勝ち上がるにはまだ力が足りない。はじめに2連勝した今回の五輪はむしろ出来過ぎで、予選リーグ最後でスロバキアに救われる形になったのが象徴的で、D組の組み合わせを見る限りもともと現実的な予想としては1勝1敗1引き分けがいいところだったろう。欧州勢がユーロ2000のためにベストチームやメンバーを送り込んでいないことを考えれば、ベスト8に入れたのは幸運の要素もある。
同時に、これまた良くも悪くも、今の日本チームが中田英寿のチームであることを再確認した大会でもあった。中田の動きが今ひとつで、とくにパスとキックが本調子ではないことは、金田喜稔ら一部の識者が予選リーグの時点から指摘していた。それでも最初の2戦でそれなりに成果を出すあたりはさすがで、特に南ア戦の2点目で高原に出したパスは文字通りの“キラーパス”の凄味があった。が、不調はアメリカ戦で最悪の形で出てしまった。あのアメリカW杯でのR=バッジオのそれとオーバーラップするような最後のPK失敗もそうだが、120分を通じて決定的なチャンスを作れず、またシュートを決められなかった。ブラジル戦、アメリカ戦で中村俊輔の動きが比較的よかったことと対照的だった。
決勝トーナメント進出という一応の成果を得たこともあって、おそらく2002年のW杯のメンバーはほぼ今回と共通の顔ぶれをトルシェ監督が率いることになる。いつもやり玉に上げられる得点力の面では、最初の3戦で1点も取れなかった柳沢や、決定機を再三逸した高原にも批判はあるだろうが、今のFWの出来はどうがんばってもあんなものだろう。日本のFWはMFやDFに比べればどうしてもタレント(才能)不足で、世界レベルのDFを1対1で抜き去るスピードや、ここ一番を決める確実性はない。これは少なくとも2002年の次の世代にならないと解決すまい。考えようによっては、決定機を5〜6回作れれば1回ぐらいは決まる。その決定機をいかに増やすか。相対的に人材のいるMFに多くを求めねばならないのは明らかだ。
今回の収穫はその2枚看板の1枚である俊輔が同格あるいは格上の相手と本気でぶつかる経験を得たことで、その意味では中田の不調もまんざらマイナスばかりではない。これに小野(浦和)が加われば、中盤に関する限り世界に通じるタレントは揃う。明らかに中盤の人材不足のブラジルに1人ぐらい貸してやっても良いのではないか? もともとDFとGKはそれなりの水準にあるのだから、FWの攻撃力をうまくMFが補えれば、W杯で決勝トーナメント(ベスト16)に入ることもまんざら夢ではないだろう。
と、ここまで書いた内容でおわかりの通り、私は基本的にトルシェ監督を支持します。同時に、日本リーグをやめてJリーグへ、というここ十年の日本サッカー界の動き自体にも、そしてそこに含まれる“企業チームではなく地域に根ざしたクラブチームを”という理念にも強く賛同します(ついでに言うと、フリューゲルスの後身である横浜FCも支持します)。
ただし、サッカー協会の一連の代表監督任免の不透明さには疑義を抱くものです。
だいたい、さかのぼれば、オフトの後のファルカン監督の解任劇からして納得いかない。いまだに、あの任命と解任の責任はうやむやのままでしょ?)
で、日本サッカーのこうした側面を鋭くえぐっててくれているのが、この本。
『惨敗』 金子達仁 幻冬社 \1600